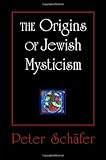- Steve Mason, "Jews, Judaeans, Judaizing, Judaism: Problems of Categorization in Ancient History," Journal for the Study of Judaism 38 (2007), pp. 457-512.
このエントリーでは、第3章と結論部分(pp. 489-512)をまとめたい。第1章では、後200年までユダイスモスという語に「ユダヤ教」という意味はなかったこと、そして第2章では、そもそも古代には「宗教」という概念すらなかったことが語られたが、第3章では、それゆえにギリシア語のユダイオス(Ἰουδαῖος)という語を宗教としてのユダヤ教の信者、すなわち「ユダヤ教徒(Jew)」と訳すのは不適切であり、むしろ民族としての「ユダヤ人(Judaean)」と訳すべきであるということが語られる。
論文著者によれば、ユダイオス/ユダイオイという語は常に「民族(ἔθνος)」としての「ユダヤ人」という意味で使われてきたという。異教徒のギリシア・ラテン作家たちの中では、たとえばストラボン、ポセイドニオス、タキトゥス、そしてディオ・カッシウスが、そしてギリシア語・ラテン語で書いたユダヤ人作家たちの中では、たとえばフィロンとヨセフスが明らかにそのような用法でこの語を用いている。
フィロンは、土地、血縁、祭儀の習慣などといった民族的なつながりの全範囲を含む意味合いでユダイオスという語を用いている。それゆえに、そうした文脈におけるconversionとは、市民権の変化において、ある民族から別の民族に「転向」するという意味であって、決して宗教的に「改宗」するという意味ではなかった。
ヨセフスは、『ユダヤ戦記』において、すでに民族としてのユダヤ人という意味でユダイオスという語を用いている。『ユダヤ古代誌』では、哲学や祭儀と密接に関わる文脈で用いることが多いが、そこからただちに「宗教」を導くことは誤りであると論文著者は述べる。さらに『アピオーンへの反論』では、ユダヤ人は、バビロニア人、エジプト人、カルデア人、アテーナイ人、スパルタ人などと比較されており、またそれぞれの民族は、故国、立法者、父祖の習慣、聖なるテクスト、祭司や貴族、そして市民権を持っているとされている。論文著者によれば、これは現代におけるインド系カナダ人や中国系カナダ人といった移民グループのようなものだという。
むろん、研究者の中には、ユダイオスを少なくともある場合には「ユダヤ教徒(Jew)」と訳すべきだと主張する者たちもいる。その代表として、論文著者はDaniel R. SchwartzとShaye Cohenを挙げている。Schwartzは、バビロン捕囚のような大きな変化によって、ユダイオスは単なる民族から宗教へとなっていったと主張するが、論文著者はどんな民族であれある程度の変化を被り、先祖伝来の政治形態を維持することに苦労しているのだから、ユダヤ人だけを特別に「宗教」へと還元する必要はないと反論する。さらにSchwartzは、『ユダヤ戦記』でのユダイオスは民族的な意味合いだが、『ユダヤ古代誌』でのユダイオスは宗教的な意味合いであるといった妥協案も出すが、論文著者は認めない。一方でCohenは、ハスモン朝の時代になると異教徒の中にユダヤ教徒へと宗教的に「改宗」する者たちが出てきたと述べるが、論文著者は、第1章で見たようにヘレニスモスという概念がそもそも文化や宗教を意味するものではないのだから、ユダイスモスだけ突然に文化や宗教の範疇に置くのはおかしいと反論する。SchwartzもCohenも、古代においてユダイオスという語の用法に途中で変化があったと考えるわけだが、論文著者は文献学上そうした変化は認められないし、もっと後代になって本当にユダヤ人に質的な変化が訪れたときには、ユダイオスではなくヘブライオスという語が使われるようになったと説明している。
こうしたことから、論文著者は以下のように結論を出している:まず、我々は古代の状況、用語、カテゴリーが自分自身のそれらとは異なっていることを知らなければならない。ユダイオス/ユダイオイに関しては、他の民族との類比において、「ユダヤ教徒(Jew)」ではなく「ユダヤ人(Judaean)」と訳すべきである。ユダヤ人は前200年から後200年にかけて民族としての「ユダヤ人」であり続けたのであって、ギリシア・ローマ時代には宗教としての「ユダヤ教」は存在しなかった。稀に「ユダイスモス」という語が使われても、それはユダヤの法や生活に向かうこと、という特別な文脈においてものみ用いられた(「ユダヤ化」)。「ユダイスモス」という語が抽象化された信仰システムとしての「ユダヤ教」という意味合いで使用されたのは、3世紀から5世紀にかけて「クリスティアニスモス」との対比においてであった。ただクリスティアニスモスという概念自体は民族、祭儀、哲学、集団、魔術システムなどの新しい集合体であったので、完全なる「宗教」概念としての「ユダヤ教」は啓蒙時代、すなわち近代の産物である。